中学受験を控えるご家庭の多くが悩むのが、
「過去問って、いつから始めればいいの?」
「まだ早い? それとももう遅い?」
というタイミングの問題です。
過去問は、志望校合格に向けて欠かせない最重要アイテムですが、始める時期や使い方を間違えると、逆効果になることも。
この記事では、「中学受験の過去問はいつから始めるべきか?」を軸に、正しい取り組み方や注意点をわかりやすく解説します。
■ 中学受験における「過去問」とは?
過去問とは、志望校が実際に出題した入試問題(過去数年分)のこと。
多くの場合、学校が公式に販売・公開しており、市販の問題集や塾の教材にも含まれます。
過去問を解く目的は主に以下の3つです:
- 出題傾向やレベルを知る
- 試験時間内での解答力をつける
- 弱点を把握し、今後の学習に活かす
■ 過去問はいつから始めるのが正解?
✅ 一般的な目安は「小6の夏休み〜9月ごろ」
多くの塾や中学受験の指導者が推奨しているのが、**「夏休み明けから秋にかけて」**のスタート。
理由は以下の通りです:
- 小6前半で基礎が一通り終わるから
- 9月以降は志望校がほぼ固まってくるから
- 実践力と時間配分を意識した勉強が必要になるから
⚠️ 早すぎると逆効果になることも
小5や小6前半の段階で過去問に取り組むと、
「難しすぎて自信を失う」「理解が浅いまま形式に慣れてしまう」
といったリスクもあります。
■ 過去問演習のステップとポイント
◎ ステップ1:まずは1年分を時間を測って解いてみる
→ 初回は「現状把握」が目的。
点数にこだわらず、形式・出題傾向・時間配分を体感しましょう。
◎ ステップ2:解説をしっかり読み込み、弱点を分析
- なぜ解けなかったか?
- どんなミスをしたか?
- 問題文のどこを読み飛ばしたか?
こうした振り返りが、単なる過去問演習を“意味ある学習”に変えます。
◎ ステップ3:繰り返し解いて、得点力に変える
- 同じ年の過去問を2回以上解く(間を空けて)
- 難度や形式に慣れることで、本番での安心感につながる
■ 過去問を解く頻度とスケジュール感
| 時期 | 内容 | 回数の目安 |
|---|---|---|
| 小6 夏休み | 志望校の形式確認・傾向分析 | 各校1年分×1回 |
| 9〜11月 | 志望校を絞って本格演習 | 各校3〜5年分×2周以上 |
| 12〜1月 | 最終仕上げ・時間管理重視 | 各校5年分以上×本番同様に演習 |
■ よくある過去問の悩みと対策
| 悩み | 対策 |
|---|---|
| 点数が取れなくて落ち込む | 点数より「なぜ取れなかったか」の分析に注目 |
| すべての学校の過去問をやろうとしてパンク | 志望度の高い学校に絞る/直近5年分に集中 |
| 同じ問題ばかりで意味があるのか不安 | 2回目以降は解法確認や時間短縮の目的で使う |
■ まとめ|過去問は「いつから」だけでなく「どう使うか」が大事!
中学受験における過去問演習は、合格への“最終仕上げ”の武器です。
焦って早く始めすぎず、でも遅れすぎないように、夏休み〜秋スタートがベストタイミング。
そして、「点数」より「分析と復習」に重きを置くことで、得点力につながります。
📌 ポイントまとめ
- 過去問の開始目安は小6夏〜秋
- 点数よりも「分析」が大事
- 志望校に絞って5年分×2周以上が目安
- 本番形式に慣れることが合格力につながる!
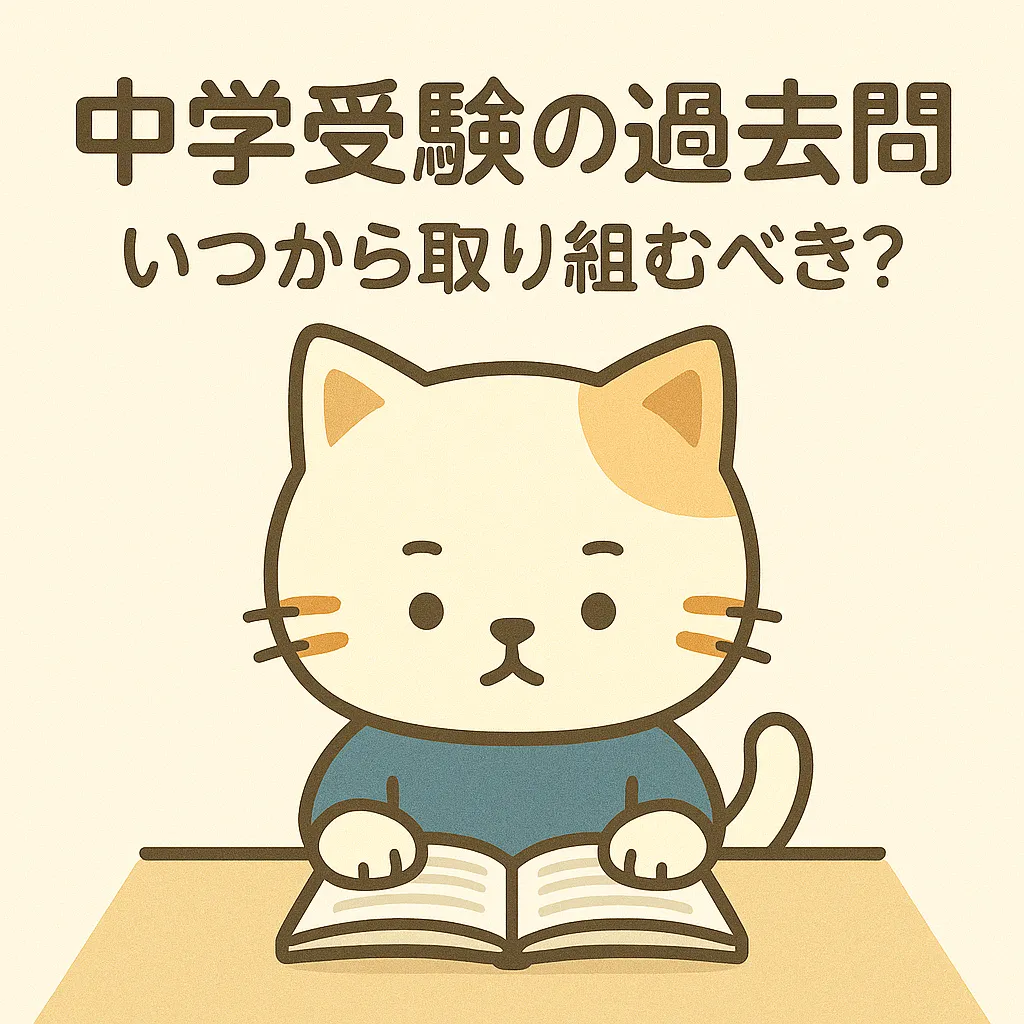


コメント